外国人参政権を巡る議論とは
外国人に参政権を認めるべきか否かというテーマは、日本において長年議論されてきました。
近年では、少子高齢化による労働力不足や国際化の進展により、永住外国人の社会参加のあり方が注目されるようになっています。
特に地方自治体における投票権(地方参政権)の付与を巡る議論が活発です。しかしその一方で、安全保障、社会の一体性、法制度の整合性など、多くの懸念も指摘されています。
外国人に参政権を認めることの懸念点
治安や安全保障への影響
国家の安全保障や治安に直結する分野において、外国人の政治参加が及ぼす影響を懸念する声があります。とりわけ外国政府と関係の深い団体やコミュニティが、特定の政治的意図をもって地域政策に介入するような事例が発生すれば、国家の主権や公共の秩序が脅かされかねません。日本は地政学的に繊細な立場にあり、こうした影響を慎重に見極める必要があります。
中国の特定の法律、特に「国家情報法」や「国家安全法」が持つ域外適用性
さて、中国では、「中国人が日本にいても、有事の際は中国の法律で動く」という懸念があります。
その懸念とは、以下の通りです。
- 中国の法律の域外適用性:
- 国家情報法: 2017年に施行された中国の「国家情報法」第7条には、「いかなる組織及び公民も、法により国家情報活動に協力し、国家情報活動が知るところとなった国家秘密を守らなければならない」と明記されています。この「公民」(国民)には、中国国外にいる中国人も含まれると解釈されており、中国政府が国外にいる自国民に対し、情報提供やスパイ活動への協力を求める法的根拠とされています。
- 国家安全法: 同様に、2015年に施行された「国家安全法」も、国家の安全保障に関わる事柄について、国内外の組織や個人に協力を義務付ける内容を含んでいます。
- 「有事の際」の解釈:
- この発言における「有事」とは、中国にとっての国家安全保障上の緊急事態や、情報収集が必要とされる状況を指していると考えられます。
- つまり、中国政府が、日本に滞在する中国国民に対し、上記の法律に基づき、情報収集活動や特定の行動を指示する可能性がある、という懸念が背景にあります。
- 日本の法律との衝突:
- 仮に中国政府が日本にいる中国国民に指示を出したとしても、その指示に従った行為が日本の法律(例:スパイ行為、不正競争防止法違反、個人情報保護法違反など)に違反する場合、その個人は日本の法執行機関による逮捕や処罰の対象となります。 日本国内では日本の法律が優先されるため、中国の法律に従ったからといって、日本の法律違反が免除されることはありません。
- この点が、中国の法律の域外適用性と日本の主権・法律との間で生じる最も重要な衝突点です。
- 個人の置かれるジレンマ:
- 日本に滞在する中国国民は、中国政府からの指示と、日本の法律の遵守という板挟みになる可能性があります。中国国内に家族がいる場合などは、指示を拒否した場合に家族に不利益が及ぶ可能性も懸念されます。
結論として、
「中国人が日本にいても、有事の際は中国の法律で動く」という発言は、中国の特定の法律が国外の自国民にも適用され、情報提供などの協力を義務付けているという事実を指していると考えられます。
しかし、日本国内においては、日本の法律が最優先され、中国の法律に従った行為であっても、日本の法律に違反するものであれば、日本の法執行の対象となるということを理解しておく必要があります。この発言は、中国の法律の特殊性と、それがもたらす可能性のある国際的な摩擦や個人のジレンマを指摘しているものと言えるでしょう。
とはいえ、現在の政治における方向性は、中国人に有利に働く事例が見られます。
顕著なのが現外務大臣の様々な発言や取り決めだと言われています。
日本人の政治的影響力の希薄化
人口比率の変化により、特定の外国人グループが政治に大きな影響を持つようになることで、本来の「国民による政治」が揺らぐという懸念も存在します。とくに外国人の多い地域では、彼らの要望が政策に反映されやすくなる一方で、日本人住民の意見が軽視される可能性があると指摘されています。
川口市のクルド人問題ですが、最近、トルコ政府が動いたことで、変化が見られるかもしれません。
あるSNSでの情報では、もし、外国人に参政権を認めると、ある地域に多くの外国人が住民登録を行い、選挙に臨むと、当然、外国人の票が優勢になる。という懸念があるとのことでした。
地方自治の歪み
地方自治体では、外国人参政権の付与により政策決定が偏る危険性があるとされています。特定の文化的・宗教的背景を持つ外国人が集中する地域では、地域独自の慣習や価値観が優先され、周辺住民との軋轢が生じることも。これは地域のガバナンスの健全性を損なう要因になりかねません。
※ガバナンスとは
ガバナンスとは、組織が健全かつ効率的に運営されるための「管理・統治の仕組み」を指します。
主な目的は以下の通りです。
- 透明性と公正性の確保
- 適切な意思決定
- リスク管理と不正防止
- 利害関係者への説明責任
これにより、組織の持続的な成長と信頼性の向上を目指します。
文化・価値観の衝突
政治的な意思決定に外国人の多様な文化や価値観が加わることで、従来の日本の政策との整合性がとれなくなる可能性があります。とくに宗教的観点やジェンダー観など、国家の根幹に関わる価値判断が問われる場面では、深刻な意見の対立が発生する可能性も否定できません。
最近の出来事をSNS等で知った限りでは、日本の公園で大声で集会を開き、地域の日本人たちが困惑しているという事例もあります。このように、日本人とは風習、宗教の大きな違いがあるのです。
SNSの有名人のひろゆき氏が、合法でない外国人は強制出国(帰国)させるべき、難民申請した時点で供託金に似た、「申請の抑止力となる金銭的な保証制度」を新たに導入したほうが良いという趣旨のことを述べていました。
※ジェンダーとは、生物学的な性別(セックス)とは異なり、社会や文化によって形成される性差や、個人が自らをどのような性として認識するか、という概念です。
法整備や国籍概念の混乱
永住者に参政権を与えることで、「国籍」と「政治的責任」の関係が曖昧になります。日本では、参政権は国民固有の権利とされており、これを変更するには憲法上の議論も必要です。また、他国との国際関係や条約との整合性も課題となり、法制度の混乱を招く恐れがあります。
外国人参政権に関する国際的な比較
諸外国の状況を見てみると、例えばフランスやドイツではEU圏内の外国人に限定して地方選挙の参加を認めているものの、国政レベルでは参政権を認めていません。
アメリカや韓国では、基本的に外国人には参政権は付与されておらず、国籍と政治参加は明確に区別されています。日本が外国人参政権について判断する際も、こうした国際的な制度との整合性を保つことが求められます。
議論のバランスと今後の課題
参政権を認めるべきだという声の背景には、「納税しているのだから発言権があるべき」「共生社会の実現」といった意見があります。一方、反対意見では「国の根幹に関わる政治参加は国民に限るべき」という主張が根強く存在しています。
今後の課題は、双方の意見を冷静に整理し、感情論を排除した上で、社会的な合意をどのように形成していくかにあります。
さて、もし、外国人が日本に移住し、世代が3世、4世となったとします。
そして、日本生まれで日本を故郷と感じている方たちが居たとします。彼らに参政権を与えるべきでしょうか・・・。
その昔、蝦夷に住むアイヌ民族が、内地と呼ばれる地域から蝦夷に進出し、やがて現在のように日本人のとなったとします。当然、参政権はありますね。
ここの大きな違いは、元々、日本国内の蝦夷という地域に住んでいたという点です。その意味では、民族の争い?において融合されたとも言えます。
では、海外からの移住者はどうでしょうか?
移住したばかりの頃は当然外国人と認識されます。しかし、前述したように100年以上が過ぎた頃、それでも外国人と認識されるのか・・・。
残念ながら、2025年の現在では、その判定は難しいようです。
他しか、「れいわ新選組」が、何世代も日本で根づいた外国人には参政権は与えても良いという見解だったように思います。この考えは正しいのでしょうか?
正解は無いようにも思えます。つまり、国家はその時代に生きる国民が作り上げていくのだと思うからです。この先、100年後、私たちは100%この世には生きていません。そして、その社会を作っているのは、これからの人たちなのです。
まとめ:外国人参政権は慎重な議論が必要
外国人に参政権を認めるかどうかは、単なる制度設計の問題にとどまらず、日本の未来を左右する重大な論点です。
短期的な利益や政治的圧力に屈することなく、国民的な議論を経て、慎重に判断していくべき課題です。多様化する社会の中で、法の整合性、公共の安定、国家主権の保全を意識しながら、丁寧な検討が求められます。

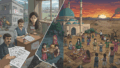

コメント