1. はじめに:選択的夫婦別姓をめぐる「なぜ」の声
選択的夫婦別姓の議論は長年続いていますが、なぜ議論は続いているのでしょうか?
本記事ではその背景と阻害要因、そして今後の展望までを分かりやすく解説します。
本記事を読む前に以下の動画をご覧ください。
よく理解できる内容です。北村靖男氏の動画を引用させていただきます。
2. 選択的夫婦別姓とは?制度の概要と目的
選択制の意味:夫婦が同姓か別姓かを選べる制度
「選択制」という言葉を具体的に説明すると、これは夫婦が結婚する際に「同じ姓(同姓)」を名乗るか、「別々の姓(別姓)」を名乗るかを自由に選べる制度のことを指します。
日本の状況
日本では現行の民法において、結婚する夫婦はどちらかの姓(通常は夫の姓にすることが多い)を選び、必ず同じ姓を名乗らなければならない「夫婦同姓」が義務付けられています。
ただし、事実婚などの形を取れば別姓を維持することは可能ですが、法律婚ではなくなるため、戸籍上の問題や法的な不便が生じる場合があります。
夫婦別姓の選択制についての日本の議論
日本における夫婦別姓の選択制についての議論は、1990年代から本格的に始まりました。
特に、1996年に法制審議会が「民法改正要綱試案」を発表し、その中で夫婦別姓を選択できる制度の導入が提案されたことが大きな転機となりました。この試案をきっかけに、夫婦別姓をめぐる議論が活発化し、以降も様々な場面で議論が続いています。
1990年代から始まったこの議論は、社会の価値観の変化やジェンダー平等の観点から、現在に至るまで継続しており、多くの国民や専門家が関心を寄せています。
※ジェンダー(gender)は、社会的、文化的、心理的な側面から見た性別を指します。生物学的な性(男性と女性)とは異なります。
3. なぜ選択的夫婦別姓が必要とされているのか?
改姓による不便と精神的負担
- 個人のアイデンティティや人格の尊重
結婚しても自分の名前(姓)を維持したいという希望は、個人のアイデンティティや人格を尊重する上で重要です。賛成派の意見では以下のような主張が挙げられます:- 名前は個人の歴史や存在そのものを象徴する
- 姓を変えることによる心理的負担
改名は「キャリア・実名の継続の困難」との意見
- キャリアに与える影響
結婚後に姓を変えると、職場での名前や肩書き、名刺、メールアドレスなどを変更する必要があり、これがキャリアの継続に支障をきたす場合があります。- 例:研究者やアーティスト、ビジネスパーソンなど、名前そのものが実績やブランドとして認識される職業では、姓を変えることで評価や信頼がリセットされるリスクがあります。
- 旧姓使用の不便さ
日本では、職場で旧姓を使用することが認められる場合もありますが、戸籍上の名前と異なるために公式文書や契約書で問題が生じることがあります。
改名は「女性への不平等感」がある
- 女性に姓の変更が偏る現状
法務省の統計によると、結婚した夫婦の約96%が夫の姓を選んでおり、女性が姓を変更するケースが圧倒的に多いです。この状況は、女性が「男性の家に入る」という古い家父長制的な価値観を引きずっているとの批判があります。- 例:「なぜ女性だけが姓を変えるのが当たり前なのか?」という疑問。
- 男性も自由に選べる環境を作る
現在の制度では、男性が姓を変えたいと思っても、社会的なプレッシャーや慣習から難しい場合があります。
※結婚時に男性が姓を変えたい例はどの程度あるのか?ごく少数ではないのか?という問題。
姓を変えるのは「結婚への心理的ハードル」が上がる
姓を変えることへの抵抗や不便さから、結婚そのものをためらうカップルも増えています。
選択制が導入されれば、結婚の心理的ハードルが下がると考えられます。
本当なのか?と思われたあなた。以下の記事をどうぞ!
いくつかの調査では、たとえば:選択的夫婦別姓を求める声が一定数存在することが示されています。
- 内閣府の世論調査
選択的夫婦別姓に賛成する人は、近年増加傾向にあります。2021年の調査では、賛成が約42%、反対が約29%という結果が出ています(残りは「どちらともいえない」)。このことから、選択的夫婦別姓を支持する人々が決して少数派ではないことがわかります。 - 結婚をためらう理由としての「姓の問題」
結婚をためらう理由として、「姓を変えることへの抵抗」が挙げられるケースもあります。
ただし、これは結婚をためらう理由の中でどの程度の割合を占めるかについては、調査によって異なります。たとえば、経済的理由やライフスタイルの変化への懸念が主な理由となるケースも多いです。
姓を変えることへの抵抗があるのは「少数派?」、その判断基準
「姓を変えることへの抵抗や不便さ」を理由に結婚をためらう人が少数派かどうかは、以下の要因によって異なります:
-
- 選択的夫婦別姓に対する意識の地域差・年代差
都市部や若い世代では、選択的夫婦別姓を支持する人が多い傾向があります。一方、地方や高齢層では、伝統的な家族観を重視する人が多い場合があります。 - 結婚をためらう理由の多様性
結婚をためらう理由は多岐にわたります。姓の問題はその一部に過ぎない可能性があり、全体としては少数派とみなされる場合もあります。 - 事実婚の増加
法律婚ではなく事実婚を選ぶカップルが増加している背景には、姓を変えたくないという理由も含まれていると考えられます。このことが、結婚そのものをためらうよりも、別の形を選ぶ人々の増加として現れている可能性があります。
- 選択的夫婦別姓に対する意識の地域差・年代差
これ、議論が進まないのなら、全国民による直接投票はどうなんだろう?
ただし、メリットと課題がある。
メリット
- 国民全体の意思を反映できる
選択的夫婦別姓は社会全体に影響を及ぼす制度であるため、国民投票を通じて直接的な意思を確認することは、民主主義の観点から公平性が高いと言えます。 - 議論の活性化
国民投票を行うとなれば、メディアや社会で議論が活発になり、制度に対する理解が深まる可能性があります。 - 政治的中立性の確保
国会や政党の利害関係に左右されず、純粋に国民の判断を仰ぐことができるため、決定に対する正当性が高まります。
課題
- コストと実施の難しさ
全国規模の投票を実施するには膨大な費用と時間がかかります。また、投票率が低い場合、結果の正当性が疑問視される可能性があります。 - 複雑な問題の単純化
選択的夫婦別姓は個人の権利や家族の在り方、伝統との調和など多面的な問題を含んでいます。これを「賛成」「反対」の二択で判断することは、議論の深さを欠く恐れがあります。 - 世論の偏りや誤解
投票前の情報提供や議論が不十分な場合、誤解や偏見に基づいて投票が行われるリスクがあります。また、感情的な議論が先行し、本質的な問題が見過ごされる可能性もあります。 - 少数派の意見が埋没する可能性
国民投票では多数決が基本となるため、少数派の権利が軽視される危険性があります。選択的夫婦別姓は「選択の自由」を求めるものであり、少数派の声を尊重する視点が重要です。
4. なぜ制度導入が進まないのか?阻害要因を深掘り
家制度・伝統観念の根深さ
日本では、家父長制的な価値観が根強く残っており、「家族は一つの姓を持つべき」という伝統的な考え方が制度導入の障害となっています。
保守派や宗教団体からの強い反対
保守的な政治家や宗教団体は、「家族の一体感が損なわれる」「伝統的な家族観が崩れる」として強く反対しています。
政府の慎重姿勢と国会の停滞
政府や国会では、慎重な姿勢が続いており、議論が進まない状況が続いています。特に保守的な政治勢力が多いことが背景にあります。
戸籍制度・皇室制度との関連
日本の戸籍制度や皇室制度が、夫婦同姓を前提として設計されているため、これらの仕組みをどう調整するかが課題となっています。
5. 海外と日本の違い:なぜ日本だけが取り残されている?
欧米・韓国・中国との比較
多くの国では、夫婦が同姓または別姓を選べる自由があります。日本のように「夫婦同姓」を義務付けている国はほとんどありません。このため、日本の現行制度は、国際的な基準から見ると時代遅れとみなされることがあります。
国連・CEDAW(女子差別撤廃委員会)からの勧告
国連の女子差別撤廃委員会(CEDAW)は、日本に対し、夫婦別姓の選択制を導入するよう繰り返し勧告しています。しかし、日本政府はこれに応じていません。
6. よくある反対意見とその論点整理
子どもの苗字はどうする?
賛成派の主張:子どもの姓は夫婦で話し合い、どちらか一方を選ぶ形にすればよい。他国でも同様の運用が行われています。
書類手続きの複雑化
賛成派の主張:現行の制度でも、事実婚や旧姓使用が認められているため、実際には大きな複雑化は起きないとされています。
家族の絆が壊れる?
賛成派の主張:姓が違っても家族の絆は保たれます。事実婚や国際結婚の家庭で実例が示されています。
7. 実際の声と事例紹介|制度導入を求める人々のリアル
- 改姓で苦労した女性の声
改姓の手続きや心理的負担に悩む女性が多いです。 - 旧姓使用ではカバーしきれない問題
職場で旧姓を使っても、公式書類では通用しないことが多いです。 - 結婚を諦めたカップルのケース
夫婦別姓を希望するために、法律婚を諦めたカップルの実例も増えています。
8. 今後の展望と必要なアクション
法制度改革に向けた議論の動向
国会での議論を推進し、法改正を目指す必要があります。
市民・企業・地方自治体レベルでの取り組み
地方自治体や企業が、夫婦別姓を選択できる環境を整える取り組みを進めています。
一人ひとりができる情報発信と意識改革
選択的夫婦別姓についての正しい知識を広め、社会全体の意識を変えることが重要です。
9. まとめ:なぜ?に対する答えと、変化を起こすために
選択的夫婦別姓の問題は、制度そのものよりも「社会の価値観の壁」に根差しています。個人の自由や多様性を尊重し、時代に合った制度を実現するためには、知識と対話、そして行動が求められます。
政党が「選択的夫婦別姓」公約にあげるのを躊躇するのは、票割れを躊躇
政党が「選択的夫婦別姓」を公約に挙げることを躊躇する背景には、票が割れるリスクを懸念する点が大きいと考えられます。以下にその理由を整理します。
1. 賛否が分かれる問題である
選択的夫婦別姓は、特に日本では賛否が大きく分かれる社会的なテーマです。
– 賛成派は、個人の権利や多様性の尊重を重視し、選択肢を増やすべきと考えています。
– 反対派は、家族の一体感や伝統的な価値観を重視し、制度変更に慎重な立場を取ります。
このように、国民の間で意見が割れる問題を公約に掲げると、支持層の一部を失うリスクがあります。特に、幅広い支持層を持つ大政党では、意見の分裂を避けるために慎重になりがちです。
ハッキリさせがたい議論なのです。
2. 無党派層への影響
選択的夫婦別姓は、特定の層に強く支持される一方で、関心が薄い層や中立的な立場の人々も多いです。
– 無党派層や政治に関心が薄い層にとって、この問題は主要な投票動機になりにくいと考えられます。
– 政党がこのテーマを前面に押し出すことで、他の重要な政策が埋もれてしまい、無党派層の支持を得る機会を逃す可能性があります。
3. 保守層との対立を避けたい
特に保守的な支持層を持つ政党にとって、選択的夫婦別姓は慎重に扱わざるを得ない問題です。
– 選択的夫婦別姓を推進することで、保守層の反発を招き、支持率が下がるリスクがあります。
– 逆に、反対を明確にすると、若年層やリベラル層からの支持を失う可能性もあります。
このように、どちらの立場を取っても一定の支持層を失う可能性があるため、政党としては公約に挙げることをためらう傾向があります。
4. 他の争点との優先順位
選挙では、経済政策や安全保障、社会保障といった国民全体に直接関わるテーマが優先される傾向があります。
– 選択的夫婦別姓は、重要な社会問題ではあるものの、現状では「経済問題」や「少子化対策」ほどの優先度が高くないと判断される場合があります。
– 政党としては、より多くの票を獲得できるテーマに注力するため、公約から外されることもあります。
5. 政治的リスク回避
選択的夫婦別姓を公約に掲げると、メディアや対立政党からの批判や攻撃の対象になる可能性があります。
– 議論が感情的になりやすいテーマであるため、政党が対立を避けるために触れないという戦略を取る場合があります。
6. 世論の動向が不安定
選択的夫婦別姓に対する世論は、年代や地域、価値観によって大きく異なります。
– 若年層や都市部では賛成が多い一方で、高齢層や地方では反対が根強い傾向があります。
– 政党としては、世論の動向が安定しないテーマを公約に掲げることにリスクを感じる場合があります。
結論
政党が「選択的夫婦別姓」を公約に掲げることを躊躇する理由は、主に票が割れるリスクを懸念しているからです。特に、支持層の分裂や無党派層への影響、保守層との対立を避けたいという戦略的な理由が大きいと考えられます。
ただし、最近では若年層を中心に賛成の声が増えているため、今後の世論の変化や社会の価値観の多様化によって、より積極的に取り上げる政党も増える可能性があります。
あなたは、どちらの考えをお持ちですか?
この記事を良いんで頂いたということは、「選択的夫婦別姓」に強烈な興味があり、真剣に考えていると思われます。
あなたのような方こそ、国政の先頭に立ち、「選択的夫婦別姓」ならずも、様々な課題に挑戦してほしいと願います。
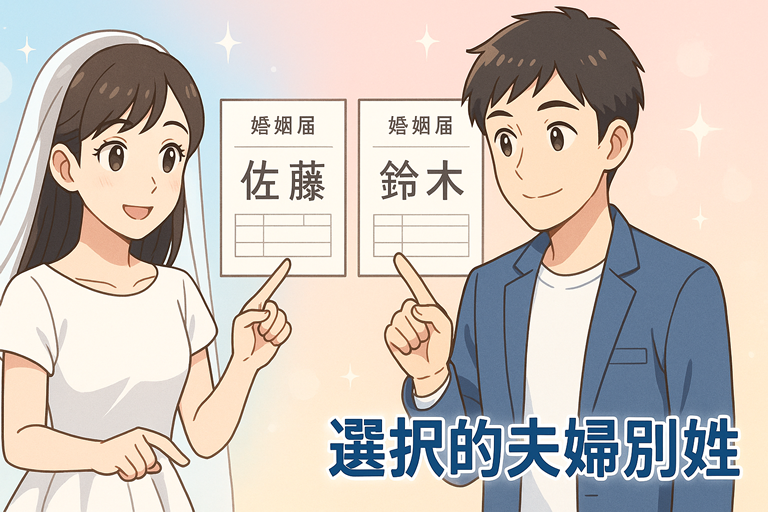


コメント